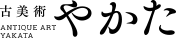茶の湯に使う茶釜や煎茶道具の茶道具出張買取を頂き、数点お譲り頂きました。
写真が28枚あります。くわしくはこちら
 高木治良兵衛の作品です。伝承 された釜師ならではの見事な模様が美しく、昔の 職人技 が施された 逸品 で買取ました。代々の高木治良兵衛の創意工夫が表現されたような逸品で、季節感の漂う面白い茶釜です。環付は蜻蛉、釜 には秋草が描かれた珍しい逸品で、茶会 ではさぞかし人気の茶釜だったと思われ買取せて頂きました。綺麗な共箱や共布も付いており、本体の釜も未使用品に近い茶道具です。また蓋は銀の摘みの替蓋が付いており、二つあります。採光の加減で白く光っておりますが、ご覧のように状態の良い品物です。
高木治良兵衛の作品です。伝承 された釜師ならではの見事な模様が美しく、昔の 職人技 が施された 逸品 で買取ました。代々の高木治良兵衛の創意工夫が表現されたような逸品で、季節感の漂う面白い茶釜です。環付は蜻蛉、釜 には秋草が描かれた珍しい逸品で、茶会 ではさぞかし人気の茶釜だったと思われ買取せて頂きました。綺麗な共箱や共布も付いており、本体の釜も未使用品に近い茶道具です。また蓋は銀の摘みの替蓋が付いており、二つあります。採光の加減で白く光っておりますが、ご覧のように状態の良い品物です。
初代 高木治良兵衛(1828年~1885年)大西家十世浄雪に兄弟で 師事 し、兄は大西家十二世浄徳を継ぎ、弟は大西家より独立し三条釜坐にて安政二年(1855)創業:初代高木治良兵衛を名乗る。現在では6代目の高木治良兵衛が継いでおられます。
茶釜(ちゃがま)の簡単な説明をさせて頂きます。
茶釜(ちゃがま)は、茶の湯 に使用する 茶道具 の一種で、茶に使用する湯を沸かすための釜のことです。風炉に用いる茶釜はとくに風炉釜(ふろがま)と呼ばれています。分福茶釜で知られるように茶釜は小さなものは直径30cm程度からあり、主に鉄で作られています。祖形の鍑が中国から伝わり日本で古くに改良され現在の形になりました。明菴栄西が廃れていた喫茶の習慣を日本に再び伝えた当時の茶は、磚茶と称される茶の葉を餅状にしたものを削ってこの鍑で煮て供しました。