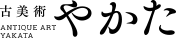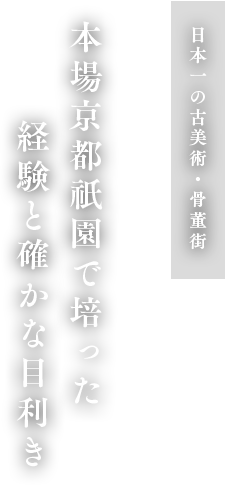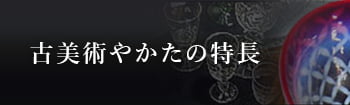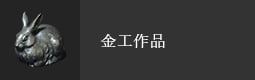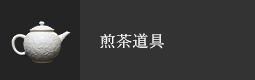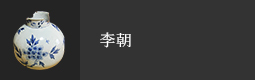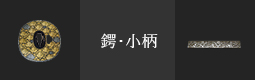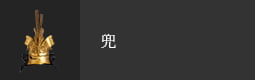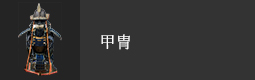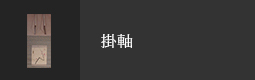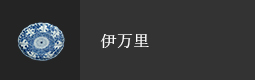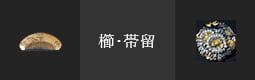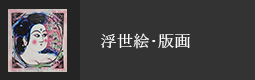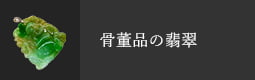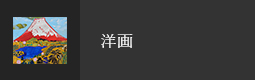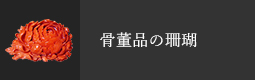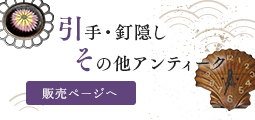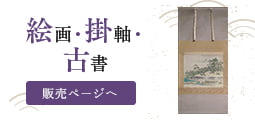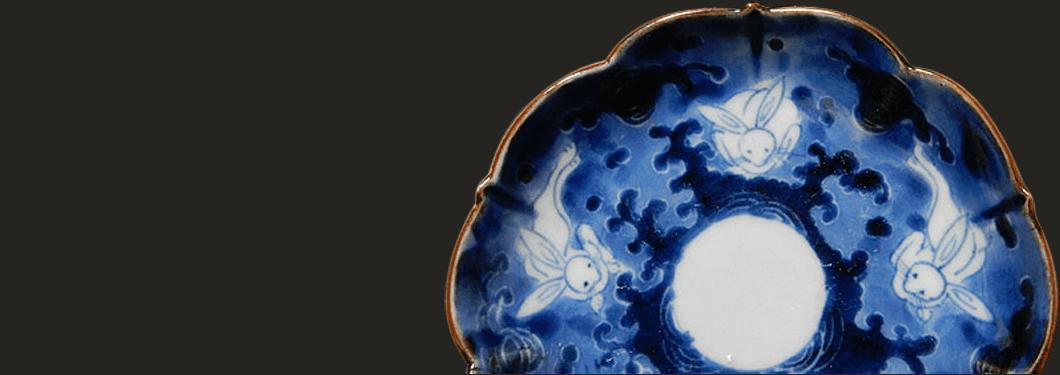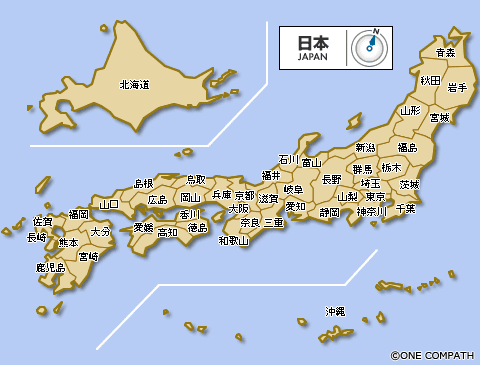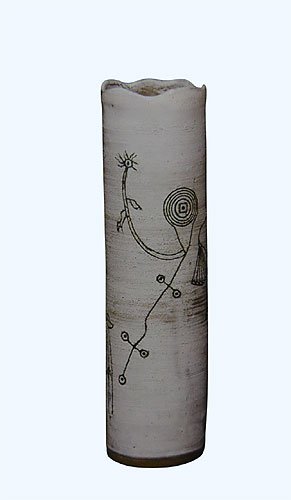河鍋暁斎 買取
河鍋暁斎は幕末から明治の激動する時代の中で活躍した浮世絵師・日本画家です。
流派に拘らず、伝統的な花鳥画や山水画、歴史画から、美人画や仏画や浮世絵、風刺画、戯画等手掛けています。
反骨精神に溢れ、画域の広さと技量には定評があり、海外の愛好家にも人気で高価買取させて頂きます。

日本一、歴史ある
京都祇園骨董街にあります。
京都は千年も続いた都です。
京都祇園骨董街の中でも当店は、歴史的保全地区に指定されています。
約80軒の古美術骨董商が軒を連ねる、
日本でもトップの祇園骨董街にある老舗の骨董店です。
京都祇園で小売販売している
老舗骨董店だからこそ高価買取出来るのです。
世界各国から1日100名近くのお客様がご来店頂いております。
店頭には買取商品を常時2000点以上展示販売しており、
愛好家やコレクターの方が品物の入荷をお待ちです。
買取依頼のお客様に納得して頂くことを
第一と考えております。
ホームページや店頭にて販売する価格を提示して、買取りさせて頂いております。
是非、ご来店頂くか、ホームページをご覧下さい。
京都祇園で昭和56年に開業、長年の信頼と実績があります。
●お譲り頂いた品物を直接販売しており、入荷をお待ちのお客様もたくさんおられます。
★古美術やかたでは、日本の古美術骨董品を後世に伝えたいと信念を貫き、半世紀営業してきました。
「品揃えが豊富で専門店にない面白味がある店」と、世界各国の美術館・博物館や愛好家の方々に来店頂き、買取から販売を一括しており、他店では真似の出来ない、独自の営業方針や特殊な骨董業界の説明をご覧ください。
河鍋暁斎の作品ー査定・買取ポイントのアドバイス
河鍋暁斎(かわなべ きょうさい)・特徴と技法

鳥瓜に二羽の鴉
1831年(天保2年)~1889年(明治22年) 58才没。
河鍋暁斎は幕末から明治中期にかけて活躍した天才 絵師 です。
下総国古河(現・茨城県古河市)に生まれるが、翌年には家族と共に江戸に移住する。
3歳で初めて蛙を描き、7歳で 浮世絵 師の歌川国芳に入門し、絵を学び始める。
その後10歳で駿河台狩野派の前村洞和に 師事、ついでその当主・狩野洞白陳信に学び、19歳にして「洞郁陳之」の 画号 をもらい修業を終える。
幕末から明治の激動する時代の中で、幕府の保護を失い、狩野派 絵師として生きることが難しかった為、「狂斎」等の画号で浮世絵、戯画、行灯 絵などを描き、苦しい時代を巧みに生き抜いた。
仏画 から戯画まで幅広い画題を描き、圧倒的な画力で独特の作品を描き上げた。
特に風刺精神が旺盛だった戯画が喜ばれたが、明治3年に政治批判をしたとして投獄される。
翌年正月に放免後、号 を「暁斎」と改め、絵師としての活動を再開する。
その後、明治9年のフィラデルフィア 万国博覧会 に 肉筆 作品を出品し、来日したフランス人実業家や 画家 のフェリックス・レガメと交流するなど、海外との交流を広げる。
明治14年には第2回内国 勧業博覧会 に「枯木寒鴉図」を出品し、日本画の最高賞妙技二等賞牌を 受賞。
この作品を 老舗 和菓子店・榮太樓總本鋪の二代目主人が100円という異例の高額で購入したことで大きな評判を呼び、以来暁斎は無数の鴉図を描いて「鴉かきの暁斎」と呼ばれるほどになった。
また、鹿鳴館を設計したイギリス人建築家ジョサイア・コンドルを弟子にし、最 晩年 にはドイツ人医師エルヴィン・ベルツが「日本最大の画家」と評価するほどの人気絵師となる。
狩野派としてのアイデンティティを誇り、伝統 的な 花鳥画、山水画、歴史画から、美人画 や仏画、浮世絵や風刺画、戯画、狂画まであらゆる画題を描き尽くした。また、狩野派 の先人達だけでなく、円山応挙にも私淑し、「鯉図」や「郭子儀図」、子犬を描いた絵画などからも積極的に学んだ。反骨精神に溢れ、画域の広さと技量には定評があり、海外でも高い評価を受けている。
河鍋暁斎の作品 画風と買取価格のワンポイント

動物の曲芸
河鍋暁斎は浮世絵師・日本画家で、その作品には、見た人々を狂気の中に誘い込み魅了するような不思議な力のある絵や、怨念を感じるような恐ろしい感覚の幽霊や地獄絵図などを描いており、高価買取対象です。
また、伝統的な仏画や山水などの画題を最新の技法を練りこんだ独自の表現方法で描いた作品や、世相を反映しユーモアを交えた戯画や風刺画などの肉筆画は高価買取させて頂きます。
絹本地(絹地)に華やかな色彩で描かれた作品が高価で、紙本地(紙地)に描かれた作品は安くなります。
河鍋暁斎は卓越した絵画技術を持ち、伝統的な 土佐派 や四条円山派をはじめ、浮世絵や西洋画に至るまで、あらゆる表現を探究し続けました。また、美人画 や 仏画、山水画、花鳥図、風刺画や戯画の制作から 挿絵 やデザインまでを手掛け、写生力や筆力のレベルも高く、海外でも高く評価されている天才絵師です。
日本画 は簡単に描かれた作品から時間をかけた力作、また大きさや 図柄 により買取価格は大きく変わります。
河鍋暁斎の場合、若書き の作品よりも、晩年 に描かれた全盛期の作品が人気で、高価買取対象です。
天保 2 年 茨城県古河市に河鍋記右衛門ときよの次男として生まれる。
天保 3 年 江戸へ移住。以後、江戸で活躍。
天保 9 年 7歳の時、浮世 絵師 の歌川国芳に 入門。
天保11年 狩野派の絵師前村洞和に再入門。
嘉永元年 現存する最初期の 肉筆 作品「毘沙門天之図」を制作。
嘉永 3 年 洞白より「洞郁陳之」の号を与えられ、卒業。
安政 4 年 琳派の絵師鈴木其一の次女と結婚し、絵師として独立する。
安政 5 年 狩野派を離れて「惺々狂斎」に改名。戯画・風刺画など 浮世絵 で人気を博す。
明治 3 年 政府批判の風刺画を描いたことで投獄される。
明治 4 年 放免後、号 を「暁斎」と改め、絵師としての活動を再開する。
明治 9 年 米国のフィラデルフィア万国博覧会に肉筆作品を出品。
明治14年 第2回内国 勧業博覧会 に「枯木寒鴉図」を出品し、日本画の最高賞「妙技二等賞牌」を受賞、菓子商の榮太樓が破格の百円で購入し話題となる。
明治15年 第一回内国絵画共進会に「風神」「雷神」を出品する。
明治22年 胃癌のため逝去、享年57歳。
河鍋暁斎の作品をお持ちのお客様、お気軽にご相談ください。
掛軸 の場合は、購入された時から入っている箱(共箱)は大切な箱で、共箱には河鍋暁斎の自筆のサインと 落款 が押されています。
共箱は、保証書も兼ねており、有る・無しで、買取価格は大きく変動します。
下記のような汚れや剥脱があっても、現状のままお持ちください。
日本画は、「蔵シミ」や「ほし」と言われる汚れが出やすく、買取価格も変わってくるので、出来ればご確認ください。
明るい所か、ライトをあてて画面を良く見てください。
鑑定書 の有無に関わらず、まず当店で無料の 真贋 の判断やアドバイスをさせて頂きますので、お電話でご相談ください。
一般的に絵画の 鑑定 は、美術俱楽部やそれぞれの指定された 鑑定機関 で行われており、その場合、真贋を問うだけで、約3万円~5万円かかり、有料です。
【所定鑑定人・鑑定機関】
河鍋暁斎の場合、鑑定機関はありません。
当店では高額な作品も扱っております、一例ですがご覧ください。
お買取りさせて頂いた作品は価格を表示してホームページや店頭で販売しています。
河鍋暁斎をはじめ買取させていただいた作家の作品も数多くあります、是非ご覧ください。
当店には河鍋暁斎の愛好家やコレクターのお客様もおられ、新しい作品の入荷をお待ちです。
河鍋暁斎の作品をお持ちのお客様は、お気軽にご相談頂ければ適切なアドバイスをさせて頂きますので、是非お問い合わせ下さい。
古美術やかたの店内写真
メディアにも多数ご紹介いただいております
クリックしてご覧ください
メディア紹介 MEDIA
- NHK国際放送で世界に紹介されました。英語版【動画】
- NHK国際放送で世界に紹介されました。日本語版【動画】
- BS朝日「京都ぶらり歴史探訪」で紹介され、中村雅俊さんご来店【動画】
- NHK京いちにち「京のええとこ連れてって」取材【動画】
- 『京都新聞』とKBS京都で鴨東まちなか美術館を紹介頂きました。
- 『和楽』7月号 樋口可南子さんがお店へ!!
- 『婦人画報』2012年5月号
- 『樋口可南子の古寺散歩』(5月17日発行)
- NHK「趣味Do楽」とよた真帆さんご来店!【動画】
- NHK『美の壺』(4月24日放送)
- 『和楽』10月号
- 『Hanako 京都案内』
- 『FIGARO japon』12月号
- 『mr partner』2011年2月号
- 2009年11月 『週刊現代』2009年11月28日号
- 『Hanako WEST』4月号
- 『骨董古美術の愉しみ方』(4月16日発行)
- 『近代盆栽』9月号
- 『Hanako WEST』11月号
- 『ORANGE travel』2006年 SUMMER
- 『婦人画報』2004年9月号
- 国際交流サービス協会に2017年6月7日紹介頂きました。
- 『Grazia』6月号
- 『VISIO ビジオ・モノ』5月号
- 『Hanako WEST』4月号
- 『gli』11月号
- オレンジページムック『インテリア』No.23
- 『MORE』12月号
- 『花時間』7月号
- 『東京育ちの京都案内』麻生圭子著 文芸春秋刊
- 『私のアンティーク』

TV出演お断りの理由は「古美術やかたの特長」や「買取のお客様必見」を詳しくご覧下さい。
日本全国対応致します、
まずはお問い合わせください
お問い合わせのお電話番号
075-533-1956
11:00~18:00(定休日:月・火)
※ご予約の買取業務は定休日も行っております。
買取は古美術やかたへ!老舗骨董店ならではの6つの技
河鍋暁斎 略歴

地獄太夫と一休
1831年、暁斎は水戸藩士・河鍋喜右衛門の次男として、現在の茨城県古川市中央町に生まれる。
翌年には一家揃って江戸に移る。3歳ですでに蛙の絵を描いた暁斎は、わずか7歳で浮世絵師の歌川国芳に 入門 し、10歳になると父である喜右衛門の薦めもあり、狩野派絵師の前村洞和に再入門した。
師である洞和は暁斎の画才を高く評価し、洞和が病で倒れた後は洞和の師家である駿河台狩野家当主・狩野洞白陳信の元で修業を続け、19歳になると洞白より洞郁陳之の画号を与えられ、浮世絵修業を卒業した。幕末から明治の激動する時代の中、幕府の保護を失い、狩野派 絵師 として生きることは難しかったことから、「狂斎」等の 画号 で浮世絵、戯画、行灯絵などを描いて糊口をしのいだ。
残酷な場面の絵画、真面目な仏画絵、風刺画、行燈絵、錦絵、戯画など、求められればあらゆる分野の絵を描いた。また、暁斎は狩野派だけでなく土佐の住吉派、円山四条派、琳派、四条派 などの 浮世絵 も学び、文人画、中国画、西洋人体図等すべての物を吸収した。惺々狂斎、酒乱斎雷酔、酔雷坊など複数の 画号 も用いる。当時、暁斎の戯画には人気があったが、筆が滑って描いた政治批判の戯画が原因で筆禍事件を起こして捕らわれる。翌年、釈放後は「暁斎」と画号を改めて 絵師 として再活動したが、美術史からも敬遠される一因となった。絵師としての活動を再開した暁斎は、国内外の 博覧会 に積極的に作品を出展した。1876年開催の米国のフィラデルフィア万国博覧会に 肉筆 作品を出展して、1881年には第2回内国 勧業博覧会 に「枯木寒鴉図」を出展して 日本画 の最高賞の「妙技二等賞牌」を受賞。
暁斎は、この作品に当時としては法外とも言える破格の「100円」の売値をつけ、「これは烏の値段ではなく、長年の苦学の値である」と言い放つと、絶妙のコメントを意気に感じた日本橋の老舗和菓子店・榮太樓總本鋪の二代目主人がそのまま言い値の100円で購入し、「百円鴉」として更に評判を呼んだエピソードがある。その後、海外との交流も広がり、英国人建築家のジョサイア・コンデルが暁斎に入門し、最晩年にはドイツ人医師であるエルヴィン・ベルツから「日本最大の 画家」と評され、人気の 絵師 となる。
岡倉天心とフェノロサらに東京美術学校の 教授 の依頼を受けることなく1889年に没した。
暁斎は当時の画家や日本に滞在・居住していた外国人との交流のみならず、神社仏閣、版元・出版社、料亭や 老舗 商店、能や歌舞伎といった広範囲にわたる人たちとの交友・受注関係を培いながら多様な作品を生み出した。
彼らとの交流の中で時代の状況を敏感に感じ取り、時に体制批判の精神を研ぎ澄まし、また一方で日本的な人間・自然観、身体観、死生観といったテーマを独自の視線で掘り下げ、屏風 や 掛軸、巻物 や画帖といった無数の作品を作り上げた。
暁斎の 弟子 には実子の暁雲、暁翠、真野暁亭、島田友春、織部暁月、早川松山、荒木白雲などがいる。
河鍋暁斎は 狩野派 だけに拘らず他の流派や画法を積極的に取り入れ、激動の幕末から明治時代を生き抜いた浮世絵師であるが、狩野派の流れも汲んだ絵師でもある。暁斎の作品には戯画や風刺画の作品も多く写生力や筆力のレベルも高く、海外でも高く評価されている 浮世絵 の画鬼である。
河鍋暁斎の主な出来事や作品の年表
天保 2年 (1831)茨城県古河市中央町に河鍋記右衛門ときよの次男として生まれる。
天保 3年 (1832)家族と共に江戸へ移住。以後、江戸で活躍する。
天保 4年 (1833)3歳の時、初めて蛙を描く。
天保 9年 (1838)浮世絵師の歌川国芳に入門、わずか7歳で浮世絵の修業に入る。
天保11年(1840)狩野派 絵師の前村洞和に 師事、師である洞和は暁斎の画才を高く評価した。
嘉永元年(1848)現存する最初期の 肉筆 作品「毘沙門天之図」を制作する。
嘉永 3年 (1850)洞白より「洞郁陳之」の 画号 を与えられ、浮世絵 修業を卒業。
「狂斎」等の画号で浮世絵、戯画、行灯絵などを描く。筆が早く忠実に描くため席画や戯画には人気がありました。
安政 2年 (1855)安政大地震の直後に、仮名垣魯文と共に世相を反映した鯰絵を出版する。
安政 4年 (1857)琳派の絵師鈴木其一の次女お清と結婚、絵師 として独立するとともに河鍋姓を継承。
安政 5年 (1858)「惺々狂斎」と号して浮世絵制作を始める。
安政 6年 (1859)芝増上寺の黒本尊院殿の修復に駿河台狩野派の一員として参加する。
万延元年(1860)この頃より多数の浮世絵 版画 を出版し、版本に 挿絵 を描く。
文久 3年 (1863)歌川派の絵師による合作「御上洛東海道」に参加。
元治元年(1864)この頃、多数の錦絵や版本を出版する。
慶応元年(1865)深山幽谷の風景を会得する為、弟子 と信州を旅する。途中、依頼されて戸隠神社中社の天井に龍図を描く。
明治 3年 (1870)筆が滑って描いた政治批判の戯画が原因で筆禍事件を起こし、投獄される。
明治 4年 (1871)放免後、「暁斎」と画号を改めて絵師として再活動する。酒乱斎雷酔、酔雷坊など複数の 画号 も用いる。
明治 6年 (1873)ウィーン万国博覧会に出品するために「鷹、蛇、雉の相食はんとする図」を描くも期日までに完成せず、
同博覧会の装飾のために大幟「神功皇后・武内宿彌の図」を依頼されて制作する。
明治 9年 (1876)米国のフィラデルフィア 万国博覧会 に肉筆作品「枇杷栖ノ島図」「中世歌妓ノ図」を出品。
来日したフランス人実業家エミール・ギメや同伴の 画家 フェリックス・レガメと交流する。
明治14年(1881)第2回内国 勧業博覧会 に「枯木寒鴉図」を出品し、日本画 の最高賞の「妙技二等賞牌」を 受賞、
百円という法外な価格で 老舗 和菓子店・榮太樓總本鋪の二代目主人が購入し話題となる。
また、近代日本建築界に多大な影響を与えた建築家ジョサイア・コンドルが 入門 する。
明治15年(1882)第一回内国絵画共進会に「風神」「雷神」を出品する。
明治16年(1883)竜池会がパリで開催した第一回日本美術縦覧会に「龍頭観音図」を出品する。
明治17年(1884)駿河台狩野派の当主狩野洞春の臨終に際し、画法を後世に伝えるよう託され、狩野派宗家の狩野永悳に入門する。
明治18年(1885)仏道に帰依して、本郷の霊雲寺より「如空」の法号を授かる、その後、絵画の 落款 に用いる。
最晩年には、ドイツ人医師であるエルヴィン・ベルツから「日本最大の画家」と評される。
明治22年(1889)4月26日胃癌の為逝去、享年57歳。
谷中の瑞輪寺正行院にある墓は、遺言により彼が3歳の時に描いた蛙の墓石が残っている。
買取作家一例
お問い合わせ・買取のご相談
(定休日:月・火)
※ご予約の買取業務は定休日も行っております。
FAX 075-571-8648
買取方法と流れ
★出張買取 出張・査定・見積り、全て費用は無料
★宅配買取 送料無料、買取価格保証
★全て現金でお支払い
買取実績 PURCHASE RECORD
老舗骨董店の当店ならでは1000点以上の買取実績を写真入りでご覧ください。
数点の八木一夫の陶芸作品の骨董品出張買取を頂き、お譲り頂きました。
京都市東山区大和大路通新門前上ル西之町197番地アクセス